JOURNAL
ゆっくり咀嚼のおすすめ!
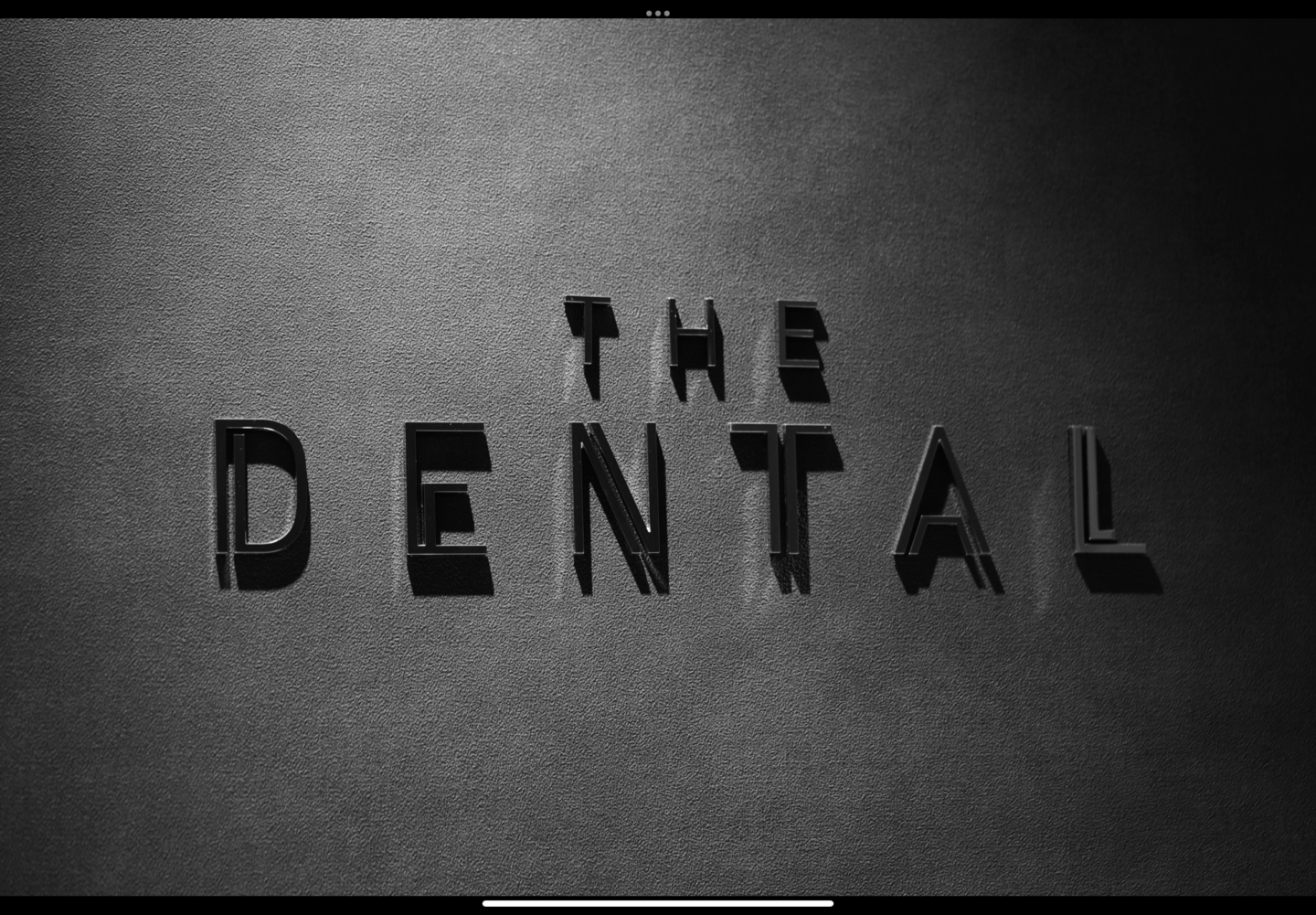
皆さま、こんにちは!
歯科助手の伊東です。
本日は「咀嚼」についてご紹介いたします!
食べ方で変わる?歯を守る“ゆっくり咀嚼”のすすめ
― 「よく噛む」ことが、想像以上に大切な理由
「よく噛んで食べましょう」
子どものころ、誰もが一度は言われたこの言葉。
けれど、大人になるにつれて忙しさに追われ、食事の時間は“作業”のようになっていないでしょうか。
実は、“食べ方”そのものが、歯や体の健康に深く関係しています。
そして、最新の研究では、「噛む」という行為が全身に驚くほどの良い影響を与えることがわかってきました。
■ 「ゆっくり噛む」は歯の健康にもいい?
食事中、私たちは自然と唾液を出しています。
この唾液が、歯を守るうえでとても重要な役割を果たします。
唾液には、
-
口の中の細菌を洗い流す自浄作用
-
酸で溶けた歯を修復する再石灰化作用
-
食べかすをまとめて飲み込みやすくする潤滑作用
といった、まるで天然の“マウスウォッシュ”のような働きがあります。
つまり、よく噛む=唾液が増える=歯が守られるという仕組みなのです。
■ 早食いの人に起こりやすい“歯と体”のトラブル
「忙しいから早く食べる」
そんな習慣が続くと、知らないうちに歯や体に負担をかけてしまうことがあります。
たとえば…
-
虫歯・歯周病が増える:唾液が減ることで、口内が乾燥しやすくなり、細菌が繁殖しやすくなる。
-
顎の筋肉バランスが崩れる:左右でしっかり噛まないため、顎関節や噛み合わせに偏りが生まれる。
-
満腹感が得にくい:脳が「食べた」と感じるまでに時間がかかるため、食べすぎや肥満にもつながる。
食べるスピードは、口だけでなく全身のリズムにも関わっています。
■ 1口30回 ― 昔ながらの習慣が理にかなっている
昔から「一口につき30回噛みましょう」と言われています。
実際にこれを意識すると、食事の味が変わることに気づくはずです。
噛むほどに、食材の甘みや旨味が広がり、香りや温度の変化まで感じ取れます。
味覚が研ぎ澄まされると、自然と濃い味付けを求めなくなり、減塩・健康効果にもつながります。
さらに、しっかり噛むことで脳が刺激され、集中力や記憶力の向上も期待できます。
「噛む」はまさに、全身のスイッチを入れる動作なのです。
■ “ゆっくり咀嚼”を身につける3つのポイント
① スマホを置いて、食事に集中する
ながら食べをしていると、噛む回数が自然と減ります。
一口ずつ味わうことで、自然と噛むリズムが整っていきます。
② 一口を小さくする
口いっぱいに入れると、早く飲み込みたくなります。
少しずつ、丁寧に噛む習慣をつけると、顎や消化にもやさしい食べ方になります。
③ 食材の“かみごたえ”を楽しむ
根菜やナッツ、海藻など、しっかり噛む食材を意識的に取り入れてみましょう。
咀嚼筋が鍛えられ、顎まわりのバランスも整いやすくなります。
■ 咀嚼と「歯の寿命」の関係
噛むという動作は、歯を単に使っているだけではありません。
歯を“守っている”動きでもあります。
しっかり噛むことで顎の骨が適度に刺激され、骨の代謝が促されます。
つまり、よく噛む人は、歯を支える骨が丈夫になりやすいのです。
逆に、噛む力を使わない生活が続くと、顎の骨が痩せやすく、歯の支えが弱くなることも。
入れ歯やインプラントでも、噛む刺激を適切に与えることが大切です。
■ 「食べ方」を変えることが、未来の歯を守る
歯の健康というと、歯ブラシやフロス、定期検診を思い浮かべる方が多いでしょう。
もちろんそれも大切ですが、毎日の“食べ方”こそ、歯の寿命を左右する基本習慣です。
ゆっくり噛んで、味わって食べる。
それは、歯だけでなく、心や体にもやさしい時間を取り戻すことでもあります。
■ まとめ ― “噛む”ことは、あなたを整える時間
現代の食生活は便利になりましたが、噛む回数は昔の半分以下とも言われています。
けれど、たった一口の意識で、唾液の量も、歯の健康も、消化も、気持ちも変えられる。
食べることは、生きること。
そして、「どう食べるか」は、どう生きたいかを映す鏡でもあります。
今日の食事から、少しだけペースを落としてみませんか?
その一口が、あなたの歯を、体を、そして笑顔を守ってくれるはずです。











